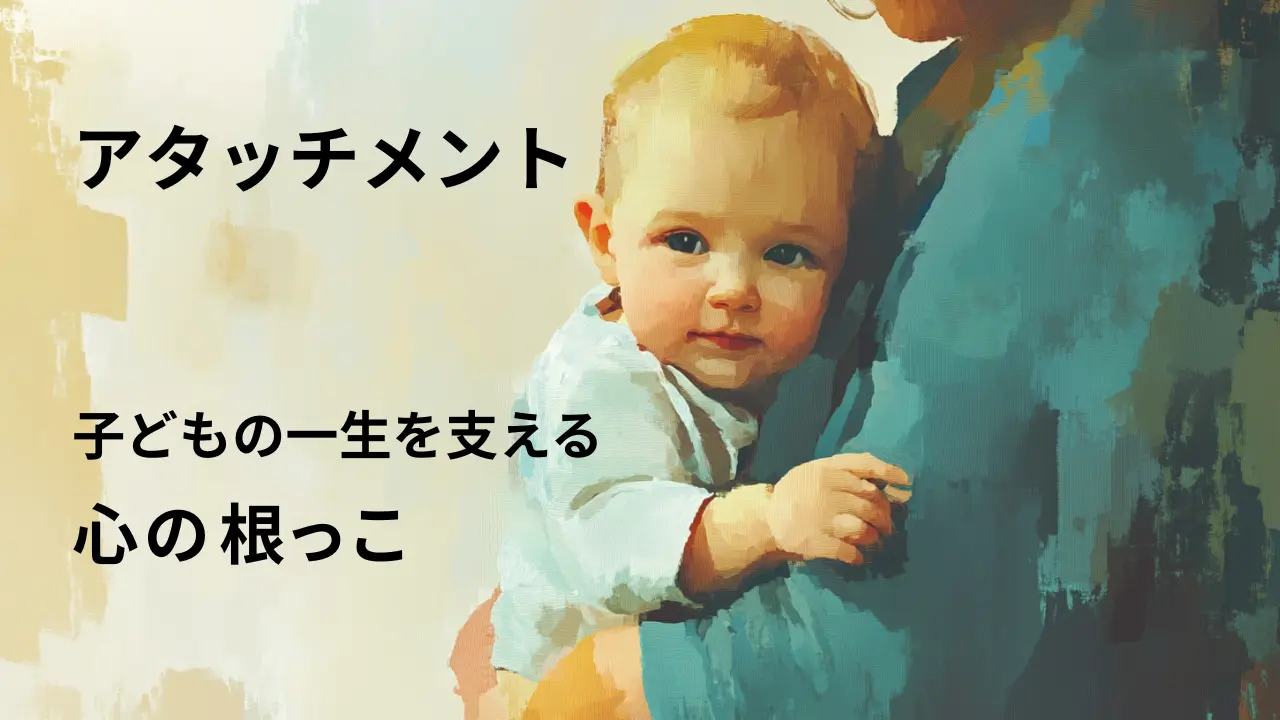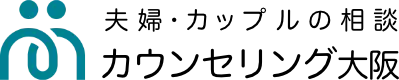子どもの心の発達において、親子の関わり方が重要な役割を果たすことは、多くの研究で明らかになっています。その中核にあるのが、アタッチメント(愛着)という概念です。
アタッチメントとは、親子の情緒的な絆のことで、子どもが「自分は大切にされている」「困ったときには助けてもらえる」という安心感を育む土台となるものです。このアタッチメントの質は、人の生涯にわたる人間関係や自尊心に影響を与えます。
※ 自尊心:最近は「自己肯定感」という言葉がよく用いられます。心理学の文脈では「自尊感情」が一般的です。このページでは「自尊心」を用います。
アタッチメント理論は、幼少期における養育者(特に母親)との絆が後の人間関係にどれほど大きな影響を与えるかを説明したものですが、近年では大人の恋愛・夫婦関係を理解するための枠組みとしても発展しています。
この投稿では、アタッチメント理論の基礎知識から、子どもの心の健全な発達のための親の関わり方について解説します。
アタッチメント(愛着)とは
アタッチメントとは、子どもが不安や恐れなどの感情が生じたときに、特定の誰か(養育者・多くの場合は母親)に身体的にくっついて、安心感を得ようとする行動や欲求のことです。
たとえば、赤ちゃんが泣いたときに抱っこされて落ち着く、幼児が怖い思いをしたときに親のそばに駆け寄る、といった行動がアタッチメント行動です。単なるスキンシップではなく、情緒的な結びつき(気持ちのつながり)という側面が重要です。
心の安全基地
子どもは養育者を「安全基地」として、外の世界を探索します。不安を感じたときにはそこへ戻って安心し、エネルギーを蓄えてはまた探索に向かう。このサイクルを繰り返すことで、子どもは健やかに成長していきます。
養育者が子どものサインに適切に応答し続けることで、子どもには「自分は大切にされている」「困ったときは助けてもらえる」という他者への信頼と自己への肯定感が育まれます。これが、生涯にわたる自尊心の強固な土台となります。
アタッチメントの4つの型
アタッチメントには4つの型があります。型の測定にはストレンジ・シチュエーション法という実験観察法が使われます。子どもと養育者を部屋に入れて、養育者だけが部屋を出て(分離場面)、後に戻ってきます(再会場面)。分離場面と再会場面での子どもの反応を見て分類します。
| アタッチメントの型 | 養育者の関わり方 | 対人関係の影響 | |
|---|---|---|---|
| 安定型 | 【安定型】 分離時には不安を示すが、再会場面ではスムーズに養育者を迎え入れ、すぐに落ち着いて再び遊び始める。 | 養育者が一貫して敏感に子どものニーズに応答する。子どもは不安時に養育者を頼ることができ、安心感を得ると再び探索活動に戻ることができる。 | 他者と健康的で信頼できる関係を築くことが得意。困ったときには他者を頼ることができ、対人関係において安定した行動パターンを示す。 |
| 不安定型 | 【回避型】 分離場面でさほど混乱を示さず、再会場面を含めて常に養育者との間に距離を置きがち。感情を表に出さない。 | 養育者が子どものニーズに拒否的だったり、無関心だったりする。子どもは不安時にも養育者に依存せず、感情を抑える傾向がある。 | 他者との親密な関係を避ける傾向がある。感情を抑えたり、自分のニーズを伝えることが苦手なため、相手との距離を保ちがちになる。 |
| 【アンビバレント型】 養育者をスムーズに受け入れられず、怒りを示したり、ぐずぐずした状態を長く引きずる。養育者にしがみつくが、同時に抵抗も示す。 | 養育者の応答が一貫していない。子どもは不安時に非常に依存的になるが、養育者の再会時には怒りや混乱を示すことがある。 | 不安定な関係を築きやすい。相手への依存と拒絶が交互に現れるため、対人関係において不安や混乱を感じることが多くなる。 | |
| 【無秩序・無方向型】 顔を背けながら養育者に近づいたり、不自然でぎこちない動きを見せたりする。すくんだり、うつろな表情のまま動かなくなるなど、一貫した行動パターンが見られない。 | 養育者が虐待的または非常に不安定な行動を示す場合に形成されることが多い。子どもは混乱した行動を示し、アタッチメントが組織化されていない状態。 | 非常に混乱した対人関係を築くことがある。相手への反応が極端になったり、予測できない行動パターンを示すことがある。 |
安定型以外の3つを「不安定型」と呼びますが、これは性格の良し悪しではなく、不安への対処パターンの違いを指しています。
上の表から分かるように、安定型の子どもは健康的な人間関係を作りやすく、不安定型の子どもは安定した人間関係を作ることに困難を抱えやすい傾向があります。
アタッチメントは生涯にわたって影響する
重要なのは、幼少期に形成されたアタッチメントスタイルは、その人の生涯にわたって人間関係のパターンに影響し続けるという点です。子どものころに築かれた「自分と他者に対する信頼感」の土台は、大人になってからの恋愛関係、夫婦関係、職場での人間関係などにも反映されます。
ただし、アタッチメントは固定されたものではありません。信頼できるパートナーとの出会いや、専門的なカウンセリングなどの「安全基地」となる経験を通じて、後天的に安定型へと変化していくことができます。これを「獲得された安定型」と呼びます。
子どもの健全な成長に必要なもの:「高い応答性」を伴う関わり

子育てにおいて、私たちはつい「物質的な豊かさ」や「理想的な環境」を優先してしまいがちです。有機食品、質の高い教育、多種多様な習い事……。もちろん、これらも子どもへの贈り物ですが、子どもの心の安定と健全な発達にとって最も重要なのは、養育者との直接的な関わりにおける「応答性」です。
質の高い時間とは「長さ」ではなく「密度」
子どもが安心感を育むために必要なのは、親と一緒に過ごす時間の「長さ」そのものではありません。大切なのは、子どもが発したサインに対して、親が敏感に、そして適切に反応する「応答性(レスポンシブネス)」の高さです。
たとえば、子どもが何かを見つけて指を差したときに「本当だ、面白いね」と共感する、不安で泣いたときに「ここにいるよ」と応える。こうした「自分の働きかけに世界(親)が応えてくれた」という実感の積み重ねが、強固なアタッチメントを形成します。
共働きの親御さんが抱く「罪悪感」について
現代では共働きが一般的になり、子どもと物理的に離れる時間が長いことに罪悪感を覚える方も少なくありません。しかし、多くのアタッチメント研究において、「保育園などの利用や、親が働いていること自体が、アタッチメントの質を低下させることはない」ことが示されています。
重要なのは、一緒にいる時間の量ではなく、「接している時の密度」です。 仕事から帰った後の10分間、スマホを置いて子どもの目を見て話を聞く。寝る前の短い時間、絵本を読みながら肌を触れ合わせる。どれだけ忙しくても、その瞬間に「今はあなたをしっかり見ているよ」というサインを送ることができれば、子どもの心には確かな安心感が育ちます。
どれだけ高価な教育環境を整えても、親子の間での「応答」が欠けていれば、子どもの心は満たされません。理想を追い求めるあまり自分を追い詰めるのではなく、目の前の子どもの小さなサインに「一対一」で応える時間を、何よりも大切にしていきましょう。
夫婦で協力して安定したアタッチメントを育む

安定したアタッチメントを育むためには、養育者個人の努力だけでなく、夫婦の協力が不可欠です。なぜなら、親自身の心が安定していなければ、子どもに対して高い「応答性」を保つことはむずかしいからです。
夫婦間のコミュニケーションが「安全基地」を支える
夫婦が協力して子育てに向き合うことは、子どもにとっての安心感を二重、三重に厚くします。子育ての方針についてオープンに話し合い、お互いの考えを尊重しながら共通理解を持つことは、家庭全体の心理的安定に繋がります。
特に重要なのは、「一方の親だけに負担を集中させない」という視点です。家事や育児の分担を整え、お互いのストレスを軽減することは、単なる効率化ではありません。一方が疲弊しきってしまうのを防ぐことで、子どもがサインを出したときに、いつでも優しく応えられる「心のゆとり」を確保するための戦略的な協力なのです。
夫婦関係は子どもにとっての「対人モデル」
子どもは、親同士の関係性を驚くほど敏感に感じ取っています。夫婦がお互いを尊重し、助け合っている姿を見ることで、子どもは「人間関係とは信頼し、支え合えるものなのだ」という肯定的なモデルを学びます。
逆に、夫婦間の激しい葛藤や冷え切った関係が日常的になると、子どもは「家庭という安全基地」が崩れる不安を感じ、アタッチメントの形成に影響が出ることがあります。夫婦関係を良好に保つ努力は、そのまま子どもの心の安定(安全基地の維持)に直結しているのです。
夫婦で取り組む実践的なアプローチ
安定したアタッチメントをチーム(夫婦)で育むために、以下のポイントを意識してみましょう。
まとめ
アタッチメントは、子どもの心の中に「安全基地」を築き、生涯にわたる人間関係や自尊心の土台となる極めて大切な概念です。
安定したアタッチメントを育むために、私たちが最も意識すべきことは、特別な教育や物質的な環境ではありません。それは、日々の小さなやり取りの中で、子どもの発信に耳を傾け、心を通わせる「応答性の高い関わり」です。
そして、その関わりを支える柱となるのが「夫婦の協力」です。一人が抱え込むのではなく、チームとして子育てに向き合うことが、結果として親自身のゆとりを生み、子どもに質の高い安心感を与えることへと繋がります。
理想の子育てを求めるあまり、最も重要な「親子の絆」や「親自身の笑顔」を置き去りにしないでください。
「今、この子の声に応える」
その積み重ねこそが、子どもが将来、自分を信じ、他者を信頼して生きていくための揺るぎない力になります。
もし、今の関係に不安を感じたり、夫婦だけで解決できない悩みを抱えたりしたときは、カウンセリングなどの専門的なサポートを頼ることも、立派な「アタッチメントの守り方」の一つです。
なお、アタッチメントは子どもだけでなく、大人の夫婦関係にも深く関わっています。夫婦関係そのものにおけるアタッチメントについては、次の記事で詳しく解説します。
- 数井みゆき (編), 遠藤利彦 (編) 2005 アタッチメント:生涯にわたる絆 ミネルヴァ書房
- 遠藤利彦 (著, 編) 2021 入門 アタッチメント理論 臨床・実践への架け橋 日本評論社
- 遠藤利彦 (監修) 2022 アタッチメントがわかる本 「愛着」が心の力を育む 講談社