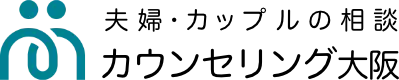不倫には、ジェンダーバイアス(性別に基づく偏見)とダブルスタンダード(二重基準)が存在します。男性は女性より不倫に寛容な傾向があります。男性の不倫より女性の不倫に厳しい傾向があります。こうした問題は明治時代の法律や社会通念によって強化され、現代に至るまで影響を及ぼしてきたと考えられます。
この投稿では、明治時代の刑法と民法に焦点を当て、それが不倫に対する男女の認識の違いをどのように形成し、家父長制や性別による不平等を支えてきたのかを考察します。また、こうした歴史的なジェンダーバイアスとダブルスタンダードが現代にどのような影響を与えているのかも考察します。
明治刑法における姦通罪の規定と男女の違い

明治時代の日本では、刑法第183条に「姦通罪」が規定されており、主に妻に対して厳しく適用されました。この法律では、妻が夫以外の男性と性的関係を持った場合、それが発覚すると刑事罰の対象となり、最大2年の懲役に処される可能性がありました。
※ 姦通とは、法律上の婚姻関係にある者が、配偶者以外の者と性的関係を持つことを指します。不貞行為と同義と考えて差し支えありません。
一方、夫に対しては異なる基準が適用されました。夫が不倫をした場合、その相手が未婚の女性であれば、法律上の罰則はなく、何人でも愛人を持つことが可能でした。夫が姦通罪に問われるのは、相手が既婚女性であった場合に限られました。
この法律は、男性の不倫に対する罪悪感が低く、女性が不倫に対して強い罪悪感を抱く社会的な背景を作り出した考えられます。夫の浮気は「男らしい」とされ、ある程度容認される一方で、妻の不倫は「家の名誉を汚す行為」として厳しく非難されました。
このような法的枠組みは、男性が不倫をしても社会的なリスクが低いと感じる一方、女性には大きなリスクと罪悪感が伴うというジェンダー間の認識の差を助長したと考えられます。
結果として、明治刑法の姦通罪は、社会全体における不倫に対するダブルスタンダードを強化し、不平等な男女関係を生み出す要因になったと考えて間違いないでしょう。
明治民法における姦通の規定と男女の違い

明治時代の民法においては、妻の姦通が発覚した場合、夫はその事実を理由に離婚を請求することができました。一方で、夫の姦通が離婚の理由として認められることはほとんどありませんでした。夫の姦通に対しては、法律上の明確な規制がなく、特に相手が未婚の女性である場合、離婚の理由になりませんした。
このように、明治時代の民法における姦通の取り扱いは、妻に対して非常に不利であり、夫には寛容なものでした。背景には当時の家父長制的な価値観がありますが、この説明は次のセクションに譲ります。
明治民法の姦通に関する規定は、妻の不倫は「裏切り」とされ、夫の不倫は「男らしさ」や「権利」の一部とする不平等なジェンダーバイアスを助長し、現在の男女間の認識の違いにも影響を与えていると考えられます。
家父長制の影響

明治時代の姦通に対する態度は、当時の家父長制的な価値観が強く反映されています。家父長制の下では、家族の名誉や血筋の維持が重視され、女性の貞操は家の名誉を守るための重要な要素とされていました。妻の姦通は「家の恥」として厳しく処罰されるべきとされました。
夫の不倫は家庭の経済的支えという役割を果たす限り、一定の範囲で容認される傾向がありました。
一方、夫の姦通には寛容な態度が取られていました。家系の存続や家族の名誉に直接的な影響を与えないと考えられていたためです。男性が複数の女性と関係を持つことは「男らしさ」や「力」の象徴とされることさえあり、その行為が家族の経済的安定を損なわない限り、社会的に大きな問題とはされませんでした。
また、妻が「夫の所有物」とされていた社会通念も、姦通に対する規定の背景にありました。女性は結婚によって夫の家に入り、夫の名誉や財産を守る役割を期待されていました。したがって、妻の姦通は「夫の所有物に対する裏切り行為」とみなされ、厳しい罰則の対象となったのです。
このように、家父長制の影響により、女性の不貞は家族全体の名誉を損なう深刻な行為とされる一方で、男性の不貞はある程度許容されていたのです。この歴史的背景が、明治時代の法律におけるジェンダーバイアスを形成し、不倫に対する男女の認識の違いを生み出す根本的な要因となりました。
明治以前の歴史的背景

明治以前の歴史的背景にも触れておきます。
古代から中世にかけて、不倫に対する法律や社会通念は地域や時代によって異なりますが、多くの場合、男女で異なる基準が適用されてきました。一般的に、女性の不貞行為は家庭や社会の秩序を乱すものとして厳しく罰せられる一方、男性の不倫はある程度容認されることが多かったようです。
日本においても、古代から江戸時代に至るまで、不倫に対する取り扱いは大きく変遷しました。古代日本では、高い身分の男性が複数の妻を持つことが一般的で、女性の嫉妬が問題視されない社会通念がありました。平安時代には、婚外の恋愛や性行為が社会的に非難されることは少なく、貴族の間では恋愛が文化の一部として受け入れられていました。
しかし、武家社会が発展する鎌倉・室町時代からは、家の血筋を重んじる価値観が強まり、女性の不倫は裏切り行為として非難されるようになりました。この傾向は江戸時代にさらに強まり、密通(不倫)は死罪とされる厳しい罰則が設けられました。特に「主人の妻」との密通は最も重い罪とされ、女性の貞操を守ることが社会の秩序維持に不可欠とされていたのです。
このように、日本の歴史において不倫に対する扱いは時代とともに変わってきましたが、常に女性に対してより厳しい基準が適用されてきたことは共通しています。こうした歴史的背景は、男女間で異なる不倫に対する認識を生み出し、現代のジェンダーバイアスにも影響を与えていると考えられます。
姦通罪の廃止とその影響

戦後の新憲法制定により、男女平等が法的に確立され、1947年に「姦通罪」が廃止されました。これにより、不倫は刑事罰の対象ではなくなり、離婚や慰謝料請求などの民事問題として扱われるようになりました。この変更は、不倫に対する法律上のダブルスタンダードを撤廃し、男女が等しく責任を負うようになったことを意味します。
姦通罪の廃止は、社会的な考え方の変化も促しました。以前は女性だけが不倫で非難される傾向がありましたが、現在では男性も含め、すべての不貞行為が平等に批判の対象となります。これにより、家父長制的な価値観が見直され、夫婦が対等なパートナーシップを築くべきだという意識が強まりました。こうした変化は、現代における不倫や浮気への法的・社会的対応にも大きな影響を与えています。
しかしながら、こうした歴史的背景は完全には払拭されておらず、男女間で不倫に対する罪悪感の違いが見られます。多くの研究や調査で、男性が女性よりも不倫に対して罪悪感を感じにくいとされる背景には、こうした過去の法的・社会的枠組みが影響していると考えられます。
実際に、家父長制的な価値観を持ち、不倫に対する罪悪感がない、もしくは小さい人に出会うことがあります。戦後生まれであっても、そのような価値観を持つ環境で育つと、その価値観が刷り込まれるのだろうと思います。
不倫に関するジェンダーバイアス(性別に基づく偏見)とダブルスタンダード(二重基準)がなくなるには、まだまた時間を要すると思います。