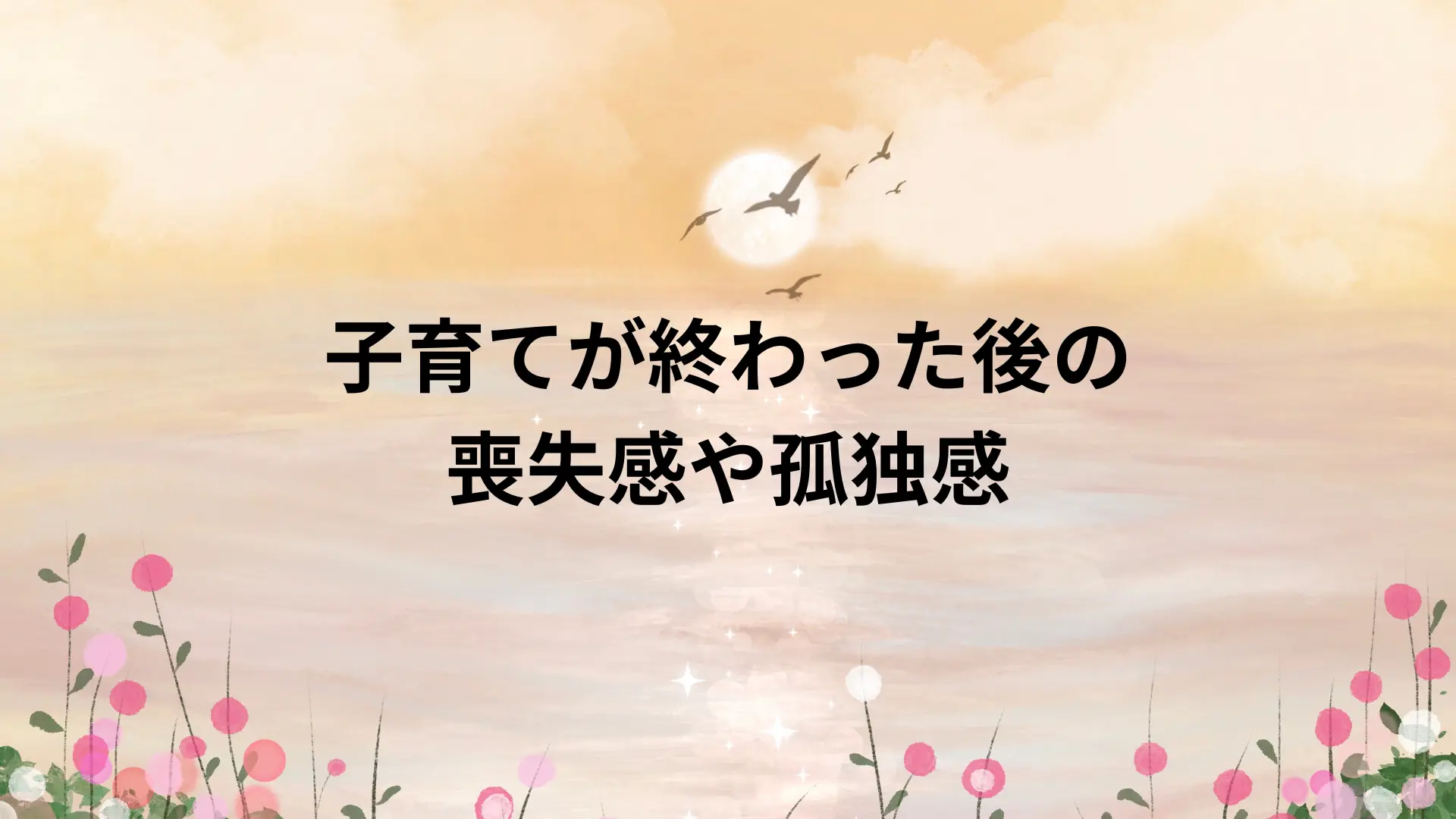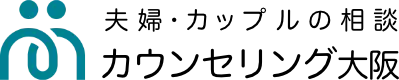子どもが独立したことで、親が喪失感や孤独感、不安感などの心の不調を経験する状態のことを空の巣症候群といいます。夫婦関係にも影響を及ぼします。
空の巣症候群とは
子育てが終わった後の夫婦関係に不安を感じることはありますか。新しい夫婦のステージに向かっているはずが、心と身体の不調で前に進めないと悩んでいることはありませんか。
子どもが独立したことで、親が喪失感や孤独感、不安感などの心の不調を経験する状態のことを、空の巣症候群といいます。 子どもが巣立ち、巣が空っぽになり、喪失や孤独を味わうことを表現した、とてもイメージしやすい言葉です。
子育てを終えた、40代から50代の女性に多く見られます。近年では、介護を終えた時期に空の巣症候群になる方も出てきています。
適応障害(ストレスとなる出来事や環境に対してうまく対処できず、心身にさまざまな症状が現れる状態)の一つと捉えられています。
空の巣症候群になりやすい人の特徴
一般的に、以下のようなタイプの人が、空の巣症候群を経験しやすいとされています。
- 努力家で何ごとも一生懸命の人:努力家で何ごとにも一生懸命な姿勢は美徳ですが、一生懸命なだけに、その対象を失ったときに、喪失感を強く感じやすい面もあります。
- 子育てが生きがいの人:自己のアイデンティティを大きく子育てと結びつけている人は、子どもが独立すると大きな喪失感を感じることがあります。
- 家庭外での交流が少ない人:友人や趣味のコミュニティなど、子育て以外の社会的な繋がりが少ない人は、子どもが巣立った後、孤独感を強く感じることがあります。
- 夫婦の信頼関係が構築できていない人:子育てを中心とした生活から夫婦二人の生活に戻る際、既存の夫婦関係の問題が顕在化しやすく、不安やストレスを感じやすいです。
これらの特徴を持つ人のすべて空の巣症候群を経験するわけではありません。これらの特徴がない人でも、状況によっては空の巣症候群を経験する可能性があります。
空の巣症候群の症状
身体症状と精神症状が見られます。症状のあらわれたかは人それぞれです。また、症状の程度も人それぞれです。
身体症状
- 睡眠障害:不眠や過眠など、睡眠パターンの変化が起こることがあります。
- 食欲の変化:食欲不振または過食といった食欲の変動が見られることがあります。
- 疲労感:特に明確な理由なく、体力的、精神的な疲労を感じることがあります。
- 心身の不調:頭痛や胃痛など、心因的なストレスが身体的な痛みや不調として現れることがあります。
中年期女性の場合、更年期障害の時期と重なることで、さらに身体の不調が悪化することもあります。
精神症状
- 喪失感:子どもが家を出たことによる深い喪失感や悲しみを感じる。
- 孤独感:家が静かになり、孤独や分離感を強く感じる。
- 不安感:将来に対する不安や、自分の価値についての不安。
- 抑うつ状態:気分が沈み、何事にもやる気が起きない、楽しむことが少なくなる。
- アイデンティティーの危機:子育てが主な役割だったため、その終わりとともに自己の役割やアイデンティティについて混乱する。
- 関係の変化に対するストレス:夫婦関係や社会的関係が変化することに対する不安やストレス。
うつ病に発展することも
これらの症状が重なり長引くことで、うつ病に発展することもあるので注意が必要です。
空の巣症候群からの回復および予防
空の巣症候群になりやすい人の特徴を知れば、自ずと回復・予防方法が導き出されます。うつ症状が見られるなど症状が重くなったときは、メンタルクリニックやカウンセリングなどの専門機関をご利用下さい。
- 家庭外の人間関係を持つ
- 家族以外のコミュニティやグループ活動に参加します。ボランティアも有力な選択肢です。
- 年を重ねるにつれて友人関係は希薄になりがちです。たまには連絡を取るなどしてメンテナンスしておきます。
- 新たな友人を作るための機会を探します。
- 夫婦関係のメンテナンス
- コミュニケーションを取ります。直接的なコミュニケーションがむずかしければ、一緒にテレビを見るでも良いので、「一緒に」を増やします。
- コミュニケーションスキルを学びます。
- 子育て中から夫婦だけの時間を大切にし、定期的にデートなどをします。
- 目標を設定する
- 新しい趣味やスキルを学ぶことで、自己実現の機会を見つけます。
- 個人的な目標を設定し、それに向かって努力します。
- 子どもが巣立つ前から、その後の生活について計画を立て始めます。
- 退職後の生活、旅行、趣味など、子育て後にしたいことリストを作ります。
回復より予防のほうが、少ないコストでリターンを得られます。メンタルヘルス全般に言えることです。
まずは、このようなことが起こりうる、このような予防法がある、と知識として持っておくことです。このページがお役に立てれば幸いです。
空の巣症候群が関わっている夫婦のカウンセリング事例
最後に、空の巣症候群が関わっているカウンセリング事例を紹介して終わりにします。
50代の夫婦。大学生の子ども二人は府外で一人暮らし。一区切りついた子育ての後、夫の隠れた借金が発覚し、関係が悪化。借金はギャンブルとキャバクラ。
妻の発言から、空の巣症候群をうかがわせる喪失感が感じられた。加えて、夫の借金による心労で、うつ症状が見られた。そのため、メンタルクリニックの受診を勧めた。
話し合いを試みても、感情のぶつけ合いで建設的な対話には至らない。カウンセラーを交えて話し合いを行いたいとのリクエストを受けて、コミュニケーションの回復から取り組みを始めた。
二人が出会って最初のデートが映画だったことが話された。カウンセラーは、2人で映画を見て、その感想をカフェで話し合う課題を出した。相手と向きあうより、相手と同じものを見る方がハードルが低いと考えてのものだった。その課題はうまくいった。
さらに、子育て期間において、お互いが本音を開示できなくなったことが語られた。
カウンセラーは、アサーティブコミュニケーションの練習を通じて、お互いの本音を開示する練習をするように誘った。徐々に本音を開示できるようになり、お互いが自然に居られる時間が増えていった。
カウンセリングは夫婦の申し出により終了。その後のフォローアップでは、多少のぎこちなさはあるものの、二人は前よりもうまくやれていると報告された。
多くのケースで問題や原因は複合的です。このケースも同様です。カウンセリングのポイントしては、原因の探索はほどほどにして、解決した状態を積み上げていくことに焦点を当てていることです。
短期療法や家族療法では、このようなアプローチを取ります。効果的かつ効率的だからです。興味のある方は、まずは一度お試し下さい。