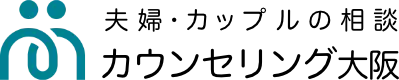夫婦関係の相談を承っていると、あるあるですが、以下のような会話の不満を訴えられたり、実際に私の目の前で繰り広げられることもあります。
妻がつらそうな表情をして言いました。
「今日ね、課長に理不尽な怒られ方して、本当に腹が立って、云々…」
夫はこう返しました。
「その課長の話をよくするやん。一度はっきり言い返してみたら」
(そう答える夫の気持ちも理解できます)
妻は言います。
「そんな簡単に言わんといてよ」
夫は続けます。
「人事部に相談するとか」
「やめたかったら、やめたらええやんって、前から言ってるやん」
少々面倒くさくなっているようです。
妻がウンザリして言います。
「そういうことじゃないねん」
「はあ…」
あるあるですが、女性は共感を求めて、男性は解決策を提示するってやつです。逆パターンの夫婦・カップルにお目にかかることもありますが、女性は共感を求めて、男性は解決に向かおうとするパターンが多いです。
「たまには聞いてくれてもええやん」と言いたくなる気持ちは理解できます。夫婦は元々は赤の他人です。コミュニケーションによって関係を育んで来たはずですから。
「たまにならええけど、しょっちゅうやん。俺は愚痴のゴミ箱ちゃうねん」と言いたくなる気持ちに共感するケースもあります。
「そもそも、共感って何ですか?」と質問されることもあります。共感について掘り下げてみます。
共感とは
「共感って何ですか?」に加えて、「同じ気持ちになるのは無理です」と言われることもあります。それはその通りです。パートナーと同じ気持ちになれない(ことが少なからずある)のは、仕方のないことです。
では、どうすれば、どうなれば、共感していると言えるのでしょうか。
共感には大きく分けて2つの種類があります。情動的共感と認知的共感です。
情動的共感は説明の通り、生得的な部分が大きく、努力でどうにかなるものではないと言えます。この能力の向上を目指しても、報われない経験が多くなります。また、パートーナーにこの能力の向上を求めると、お互いがつらくなる機会が多くなります。
認知的共感は意識的な努力で向上が見込めます。共感力を向上したいと思ったとき、焦点を当てるべきはこちらです。
共感的に「理解」する
私がカウンセラーとして、クライエントさんのお話しをお伺いする際には、まずは、気持ちや考えを「理解」することに注力しています。理解してこそ、「クライエントさんの立場になったら、どう感じるだろう」と想像できるはずです。少なくとも私はそうです。
カウンセラーが備えておくべき姿勢の一つに共感的理解があります。言葉は共感、理解の順ですが、実践では理解が最初に来ます。
応用編になりますが、共感的理解の例を紹介します。
夫婦カウンセリングでは、不倫のような大きな問題を扱う機会が多くあります。不倫された人がパートナーに、「どうして、不倫なんかしたの!」「なぜ、子どもがうまれたばかりなのに、そんなことができるの!」と質問の形で感情をぶつけるときがあります。
当たり前の話ですが、質問されると返答します。
「どうして、不倫なんかしたの!」と問われると、「軽い気持ちでしてしまった」などと答えるかもしれません。多くの場合、求めているのはそんな反応ではありません。
カウンセラーは、少なくとも私の場合は、「その質問をするのはどのような気持ちからだろうか」「その質問で何を訴えようとしているのだろうか」と考えます。
信頼を裏切られた気持ち、ワンオペでがんばっていた気持ちを踏みにじられた、等々の気持ちを表す言葉が見つからず、質問の形になったのかもしれません。
「このような気持ちでいらっしゃるかもしれませんね」と確認しながら、まだ言葉にされていない、もしくは表現する言葉が見つかっていない気持ちを言葉にする営みを重ねていきます。
「気持ちをわかってもらえている」という体験が回復の第一歩となるからです。カウンセラーは、この共感的な理解を通じて、クライエントさんとの信頼関係を築いていきます。
この例の共感は、認知的共感です。お話しをお伺いする中で、情動的共感も起きてはいますが、それは自然に起きているものです。意識しているのは、頭で理解して気持ちを想像することです。
共感力を高めるためには
もちろん、目指すのは認知的共感の向上です。
「理解された」という実感は、心に安心感をもたらします。問題そのものは何も変わっていなくても、誰かが自分の気持ちを理解してくれているという体験は、緊張や不安を和らげ、心の安定につながります。
先ほどの例でも触れた通り、カウンセリングの場面でも、クライエントさんが「この人は私の気持ちをわかってくれている」と感じることで、心が落ち着き、自分で問題に向き合う余裕が生まれてきます。
日常生活で実践できる取り組みを紹介します。
一つ目は、積極的傾聴です。「うんうん」とうなずきながら、「へえー」などとあいづちを入れながら聴くことで、相手は話しやすくなります。「ちゃんと聞いていますよ」というメッセージが伝わります。
「それで、どうしたの」「それから、どうなったの」と先を促します。理解しようとする姿勢を示せます。そして、話を最後まで聴くことに徹します。理解に徹します。解決策は棚上げします。解決策は、求められたときだけ提案します。
二つ目は、感情の受け止めです。「そう感じるのは当然やね」「そんなことがあると、つらいね」といった言葉で、相手の気持ちを受け止めます。同じ気持ちになる必要はありません。「あなたの立場なら、そう感じるのも理解できる」という姿勢です。
三つ目は、理解の確認です。自分の理解が正しいかどうかを確認します。「こんな風に感じてたの?」「こんな気持ちになったのかなと思ったけど、合ってる?」というように確認します。この積み重ねが認知的共感につながります。
コミュニケーションは言葉だけで行うものではありません。口調や姿勢、視線などの非言語コミュニケーションも重要です。うなずきやアイコンタクトで、「ちゃんと聴いている」という気持ちが伝わります。
最後に

共感について理解を深めてきましたが、ポイントをまとめておきます。
今回は共感を掘り下げることに絞って進めてきましたが、2人のコミュニケーションをより良くするには、共感以外にも取り組めることが多数あります。以下はコミュニケーション向上をテーマとしたブログの一覧です。一読いただければ幸いです。