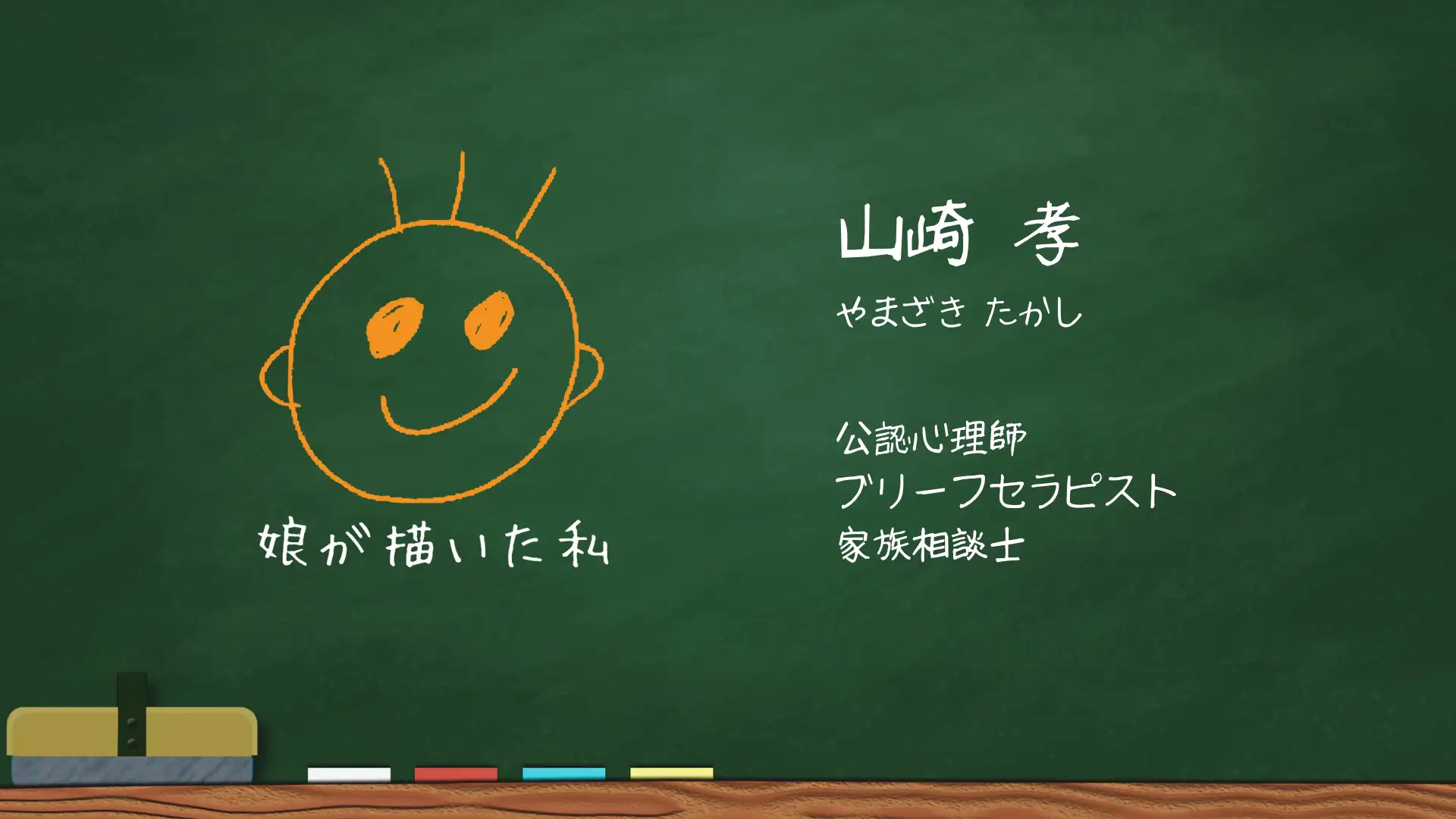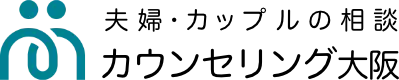カウンセラーとして
民間企業勤務、個人事業を経て、2011年よりカウンセラー業を始めました。夫婦・カップルへの家族療法カウンセリングは、私自身が夫婦関係で悩み、回復を経験したことも背景にあります。
これまで多くの夫婦関係のご相談に携わってきました。述べ7,000回超(個人カウンセリングを含む)の経験があります(数年前からカウントするのをやめたので実際はもっと多いです)。
2018年頃の私は今より膨よかでした。
最近の私

カウンセリングについて
カウンセリングの学びは来談者中心療法(傾聴)から始めました。「指示を出すのではなく、相談に来られた方が自分自身の力で答えを見つけることを支える」という姿勢に共感しました。
やがて、話を聴くだけでは支えきれない場面にも出会い、認知行動療法を学びました。考え方や行動のクセを見直し、生活に変化を生み出す支援を取り入れるようになりました。
さらに家族療法とブリーフセラピーを中心に据えるようになりました。
家族療法は、問題の原因を特定の個人に求めず、関わり合いの中に目を向けるアプローチです。「問題の責任を一人にしない」という人にやさしい考え方に共感しています。ブリーフセラピーは短期間での変化を重視し、小さな工夫や一歩を積み重ねていく支援を行います。
理論と技法を学びながらも、私自身の経験をツールの一つとして大切にしています。自らも夫婦関係の苦しみを経験したからこそ分かる気持ちがあります。ただし、それを一方的に当てはめるのではなく、あなたの物語に耳を傾け、共に考えていくことを何よりも大事にしています。
参考ページ:夫婦・カップルカウンセリングについて(家族療法・ブリーフセラピー・認知行動療法について簡潔に説明しています)
資格
所属
学術団体の研究員としてスーパービジョンに継続的に参加し、研修や講習を通じて研鑽を続けています。
屋号「フルフィルメント」について
「フルフィルメント(fulfillment)」には、一時的な達成感だけでなく、内面の満足感や深い充実感の意味があります。問題の解決だけに留まらず、自分らしく心を満たし、人生に充足を得られるサポートを届けたいという思いを込めています。
理念とミッション
支え合い、成長し続ける夫婦関係を築くために
詳細ページ:夫婦カウンセリングの理念
カウンセラーとしての研鑽
カウンセリング業を始めて痛感したのは、スキルを学ぶだけでは十分ではないということです。
スキルには即効性があります。技術を学び、練習を積み重ねることで、「心が軽くなりました」と満足していただけるカウンセリングは、1、2年(500〜1,000時間)程度で提供できるようになります。
しかし、その先に進むためには、理論と実践を行き来する学びが欠かせません。
理論とは、多くの人々を支援するために整理された知見の地図のようなものです。単に自分の経験や感覚に頼るのではなく、さまざまなケースに柔軟に対応するための確かな根拠になります。地図があるからこそ、迷ったときに立ち戻り、軌道修正ができます。
もちろん、理論を学んだからといって、すぐにカウンセリングの力が飛躍的に高まるわけではありません。それでも、長く支援を続けていくためには、理論とスキルを結びつけ、磨き続ける姿勢が大切だと考えています。
私は家族療法・ブリーフセラピーを中心に、さまざまな心理学的理論を学んできました。これらは、クライエント一人ひとりの状況や課題に合ったサポートを行うための大切な土台です。
具体的には、所属する学術団体のスーパーバイザー(経験・知識が豊富なカウンセラーで、他のカウンセラーを指導・支援する立場の人)の指導を継続して受けています。スーパービジョンを通じて、自分の支援が適切であるか、より良い方法はないかを常に振り返る機会を持っています。また、学術団体主催の研修や講習にも定期的に参加し、新しい知見や技術を学び続けています。
これからも研鑽を重ね、一人ひとりのクライエントにとって、安心できる場と確かなサポートを届けていきたいと思っています。
私の夫婦関係
結婚生活は順風満帆ではなく、私も仕事の苦しさやうつ病を経験し、夫婦関係に悩んだ時期がありました。向き合えず、支え合うことができない時期もありましたが、子どもを一緒に応援する中で少しずつお互いを理解し、支え合う関係を取り戻すことができました。そうした経験が、今の支援の原点です。
夫婦関係は心の安心の土台であり、家族の安全基地です。その大切さを実感してきたからこそ、一緒に考え、支える立場でありたいと思っています。