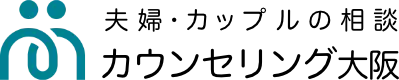夫婦ケンカの原因の一つに、常識と常識のぶつかり合いがあります。異なる環境で育って生きてきたのだから、お互いの常識が異なるのは当然とわかっています。とは言うものの、頻繁に繰り返されたりすると、受け入れるのがむずかしいことがあります。
会社員時代、上司と私の常識の差が大きくて苦労したことがありました。自分の判断で動くと悉く上司の考えから外れます。まず上司の判断を仰ごうとすると、「常識の範囲で考えろ」と返ってきます。私の常識で考えると上司の常識から外れました。結構疲れました。
そもそも、常識って、誰がどのようにして決めるのでしょう。
現実とは客観的なものではなく社会的に構成されたもの
社会構成主義という概念があります。比較的新しいものですが、心理療法の分野にとどまらず、教育や組織開発の分野でも活用されています。以下のように説明されます。
- 意味や現実は客観的なものとして存在するのではなく、人々の対話によって作られたもの。
- 現実と認識しているものは社会的に構成されたもの。そこにいる人々が合意することによって現実となる。
- 人は自分の持つ認識の枠組みや知識を使って世界を理解し、自分なりの意味を生成する。
例を上げてみます。以下のマグカップは私が普段使用しているもので、100均で購入しました。

このマグカップについて、以下のような会話が交わされたとします。
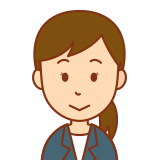
感じのいいマグカップですね。

ありがとうございます。実は100均なんです。
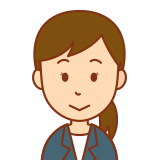
100円とは思えないクオリティですね。
この会話によって、あのマグカップは100円には見えないクオリティであるという意味が構成されました。
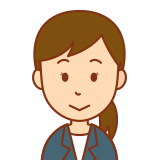
いかにも100均というクオリティですね。

わかりますか…
このような会話の後には、100円クオリティのマグカップという現実が構成されます。
常識とはコミュニティに属する人たちの間で合意したもの
常識も同じように構成されたものかもしれません。日本国民の多数が合意したものが日本の常識。大阪府民の多数が合意したものが大阪府民の常識。それは東京都民の常識と異なることもあるでしょう。吹田市民の多数が合意したものが吹田市民の常識。それは岸和田市民の常識と異なることもあるでしょう。
同じ吹田市民でも異なる常識を持つ人がいて当然でしょう。コミュニティの最小の単位が家族とすると、それぞれの家族には、それぞれの常識があって当然です。それはおそらく事実でしょう。
じょう しきじやう—[0]【常識】
①ある社会で、人々の間に広く承認され、当然もっているはずの知識や判断力。「━では考えられない奇行」「━に欠ける」
大辞林4.0(iPhoneアプリ)編者:松村 明 三省堂編修所 2019
正義と正義がぶつかって争いになる
常識は多数が合意していることであって、絶対的に正しいことでありません。しかし、長年慣れ親しんでいるうちに、絶対的に正しい感覚になることがあるようです。お互いの実家の常識(正義)のぶつかり合いが夫婦ケンカの原因になることがあります。
新しい文化・常識を作るスタートが結婚
結婚とは、お互いが育ったコミュニティの文化が融合して、新しい文化を作っていくスタートと考えることができます。夫婦ケンカを新しい文化・常識を作るプロセスと考えたら、決して不毛なものではなく、むしろ有益なものと捉えることができます。
「危険」と「機会」を合わせると「危機」です。夫婦ケンカは関係を壊す危険なものにもなり得るし、関係を発展させる機会にもなり得ます。機会にする鍵は、合意にたどり着くコミュニケーションです。