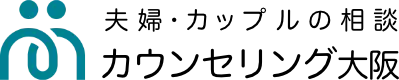このページの内容は、下園壮太先生(メンタルレスキュー協会理事長)の「感情ケアプログラム」を元にしています。
怒りの対処はアンガーマネジメントがよく知られていますが、私は「感情ケアプログラム」をおすすめしています。「感情ケアプログラム」について詳しく知りたい方は、講座を受講するか、下園壮太先生の著書『人間関係の疲れをとる技術』をお読み下さい。
当相談室のカウンセラーの山崎は「感情ケアプログラム」の指導者コースを修了しています。プログラムを取り入れたカウンセリングが可能です。
怒りに影響を与える要素
怒りのコントロールには、3つの段階とそれぞれの段階に応じたスキルがあります。怒りに影響を与える要素を認識してから読み進めると、それぞれのスキルが意味することを理解しやすくなると思います。
下園先生によると、怒り(に限らず感情全般)に影響を与える5つの要素があります。①感情の3段階、②忘れる対処、③恨み記憶、④疲労・体調不良、⑤自信の5つです。
疲労が蓄積していたり、体調が悪いときには、気持ちに余裕を持つのがむずかしく、ちょっとしたことでも強く反応しやすくなります(体調管理については、ここでは触れません)。
自信がないとは、出来事や状況が自分の手に負える範囲を超えている感覚です。自信がない人は、危機に備えて敏感にアンテナを張っています。刺激に敏感に反応しやすく、怒りやすい状態にあります。自信が育つと過剰反応が少なくなります。怒りも適度になります。感情に適切に対処できると自信が育ちます。自信は大きなテーマなので、ここでは取り上げません。
怒りケアの心構え
怒りのコントロールに取り組むに当たって意識しておきたいことがいくつかあります。
(1)問題解決は後回しにして感情のケアを優先する
(2)完全な解消ではなく解消に向かうプロセスを進める
(3)習得には練習が必要
(1)問題解決は後回しにして感情のケアを優先する
1つ目は、問題解決は後回しにして、感情のケアを優先することです。
怒りは、自分が絶対に正しいと確信させます。勝ち負けにこだわって、心と身体が戦う姿勢になります。小さな刺激に大きく反応します。怒りは対人関係の相互作用で悪化します。怒りを向けられた相手は怒りで対抗するか、距離を置こうとします。どちらもさらなる怒りを招きます。
このような状態で建設的な話し合いをするのは困難です。解決への話し合いを試みて、かえって状況を悪化させてしまいがちです。まずは感情をケアすることです。解決の取組はその後です。
(2)完全な解消ではなく解消に向かうプロセスを進める
2つ目は、怒りの完全な解消を目指すのではなく、解消に向かうプロセスを進めることです。感情の3段階で触れますが、すべての感情には、必要な強度と継続期間があります。すぐに解消されるものではありません。
プロセスを進めるのは、恨み記憶として残さないためでもあります。恨み記憶とは、「前にもこんなことがあったな」「いつもこんなことを言われる」といった類いの記憶です。些細なことで強い怒りを感じるのは、その瞬間の怒りに、恨み記憶による怒りが加わるからです。
怒りの対処法として、「我慢」や「忘れる」があります。怒りが沸騰しているときは、グッとこらえてその場を離れることが望ましい対象の一つです。しかし、「我慢」だけで終わると不快な記憶が残ります。これが恨み記憶として残ります。
「忘れる」も似たことが起こります。完全に忘れているわけではありません。表面上は忘れていても、ちょっとしたきっかけで恨み記憶がよみがえります。恨み記憶として残さないために、「我慢」や「忘れる」で終わらせずに、解消へのプロセスを進めることが必要です。
(3)習得には練習が必要
カウンセリングを受けに来られる方は、まさに今、問題を抱えているわけですから、ほとんどの方が即時に解決することを望まれています。しかし、即時に容易に解決に至る魔法はありません。怒りのケアはスキルです。スキルを身につけるには練習が必要です。
感情の3段階
感情ケアプログラムにおいては感情を、①危機対処<3倍反応モード>、②警戒<2倍反応モード>、③予防<通常反応モード>の3段階で捉えます。そして、それぞれの段階に応じたケアを行います。
① 危機対処<3倍反応モード>
いわゆる、闘争・逃走反応の状態です。危機に直面したとき、闘うか逃げるかして、活路を見出そうとする反応です。危機に直面しているわけですから、余計なことを考えているヒマはありません。思考は停止します。この状態では、刺激に対して大きく反応します。危機に対処するためにセンサーが敏感になっています。些細なことにも過剰に反応します。通常時より3倍くらい強く反応するので<3倍反応モード>と呼んでいます。
この状態で話し合いを試みても、ほとんどの場合、お互い過剰に反応して、さらに状況を悪化させることが多いです。怒りが沸騰してるときは、相手の何気ない言葉にも、強く反発するものです。
② 警戒<2倍反応モード>
強い怒りは収まっているものの、完全に落ち着きを取り戻すには至らず、ピリピリしている状態です。通常時より2倍くらいの強さで反応するから<2倍反応モード>です。この段階で何も起こらなければ、徐々に予防段階へ向かいます。この段階で不快な刺激を受けると、危機対処に戻ります。
③ 予防<通常反応モード>
平穏な状態、冷静な状態です。物事を様々な角度から見て、柔軟に捉えることができるのはこのときです。
感情の段階に応じたケア
感情は「危機対応」⇒「警戒」⇒「予防」の順に落ちついていきます。怒りのケアは、このプロセスを促進させることを目的とします。促進するために、それぞれの段階に応じたケアを行います。
それぞれの段階に応じたケアとは、「危機対応」では感情を『下げる』こと。「警戒」では感情に『触れる』こと。「予防」では『考える』ことです。
① 危機対処<3倍反応モード>のケア『下げる』
この段階の特徴は、勝つか負けるか・戦うか逃げるか、<3倍反応モード>です。ここでのケアは『下げる』です。『下げる』とは、熱いお湯を冷ますイメージです。
具体的には、追加の刺激を入れないことです。刺激に対して3倍の強度で反応してしまうからです。状況の悪化を防ぐこと。熱くなった怒りを冷ますことが先決です。そのために、相手から距離を取って一人になるのが有効です。
一人になったら、「呼吸法」や「漸進的筋弛緩法」によって身体を緩めます。身体を緩めることによって感情を緩めます。人は怒り(などの強い感情)に包まれているとき、呼吸は浅くて早く、身体は力が入っています。リラックスしているとき、呼吸はゆったりと深く、身体の力は抜けています。
怒り ⇒ 浅くて早い呼吸・力が入った身体
リラックス ⇒ ゆったり深い呼吸・力が抜けた身体
ゆったり深い呼吸をして、感情を冷ますのが「呼吸法」です。身体の力を抜くことによって、感情を冷ますのが「漸進的筋弛緩法」です。具体的なやり方は、大阪府のホームページにアップされているリーフレット(PDF)がわかりやすいです。
「呼吸法」で大切なのは「吐く」です。息を吐くときに副交感神経が刺激されてリラックスに向かいます。お腹でしっかり吐いて、軽く吸ってを『下がる』が実感できるまで繰り返します。
「漸進的筋弛緩法」は身体の力を抜くことによって気持ちを緩める方法です。まず身体に力を入れます。次に力を抜きます。それを身体のパーツ毎に行います。肩であれば、最初に力を入れて5秒ほどグッーと上げます。次にストンと力を抜いて、10秒ほど脱力感を味わいます。それを繰り返しながら、リラックスに向かいます。
気軽にリラックス | 大阪府(PDFファイル)に詳しいやり方が紹介されています。参考にして下さい。
上記のリーフレットには「自律訓練法」も紹介されていますが、「自律訓練法」は指導を受けた上で練習を行わなければ要領をつかむのがむずかしいため、ここでは省きます。「呼吸法」と「漸進的筋弛緩法」も練習が必要ですが、一人でリーフレットを見ながらの練習でも効果を実感しやすいです。
「呼吸法」や「漸進的筋弛緩法」でなければならないということではありません。あたたかいお茶を飲むでも、音楽を聴くでも、『下げる』ことに役立つなら何でもOKです。相手から距離を置くなどして追加の刺激を入れないようにして、怒りを『下げる』対処をすることが、この段階のケアです。
② 警戒<2倍反応モード>のケア『触れる』
この段階の特徴は、強い怒りは収まっているものの、完全に落ち着きを取り戻すには至らず、ピリピリしている状態です。
イヤなことを考えないようにしたり、忘れようとして凌ごうとすると、このピリピリ状態が続き、穏やかな状態に至るプロセスが止まってしまうことがあります。常にピリピリして、ちょっとしたことでも怒りやすい状態が維持されます。
考えないようにしたり、忘れようとするのは、自分自身を否定することにつながります。怒りが生じたのは事実ですから、正しいか間違いかの評価をせずに、怒りという感情を認めましょう。
プロセスを進めるには、自分からあえて感情に触れます。そのときの怒りをあえて思い出して、触れてみます。怒りに乗っ取られそうになったら一旦中断して、「呼吸法」や「漸進的筋弛緩法」などで整えます。これを繰り返します。
どのように考えたらいいのだろう?など考える必要はありません。むしろ考えてはいけません。それは次の段階で行います。ただ感情に触れて感じるだけです。これを繰り返すことによって、危機に対処するセンサーが落ちついていきます。
触れることをせずに、我慢したり、考えないようにしたり、忘れることで対処しようとすると、その出来事は恨み記憶になります。恨み記憶は「同じようなことが起きたら」とセンサーを敏感にします。恨み記憶として残さないために『触れる』というケアを行います。
③ 予防<通常反応モード>のケア『考える』
冷静な状態です。物事を多面的に見て考えることができます。この状態で、怒りが生じやすい思考の偏りに取り組みます。認知療法的な取り組みを紹介します。
認知とは、考えや受け取り方のことです。私たちは、相手の言動など出来事が怒り(などの感情)を作ると考えがちです。しかし、同じ出来事でも感じ方は人それぞれです。ということは、出来事と感情の間に、その人特有のフィルターのようなものがあるはずです。そのフィルターが認知です。
×出来事 ⇒ 感情
○出来事 ⇒ 認知 ⇒ 感情
例を上げてみます。
昨日の夕方、駅で友人を見かけたので声をかけました。ところが、友人は反応せずに素通りしてしまいました。
Aさんは、このように感じました。
<出来事>友人が素通り
⇒<認知>無視して失礼
⇒<感情>怒り
Bさんは、このように感じました。
<出来事>友人が素通り
⇒<認知>怒っているのだろうか
⇒<感情>不安
Cさんは、このように感じました。
<出来事>友人が素通り
⇒<認知>私って、いつもこう
⇒<感情>悲しみ
Dさんは、このように感じました。
<出来事>友人が素通り
⇒<認知>何か考えごとでもしてるのかな?
⇒<感情>(友人を)心配
Eさんは、このように感じました。
<出来事>友人が素通り
⇒<認知>聞こえなかったのかな
⇒<感情>穏やか
Eさんのように考えなければならないということではありません。5つすべてに可能性があります。色々な可能性の中から、その状況で現実的な認知を選択できるように練習します。カウンセリングで取り組むのが望ましいですが、ハードルの高さを感じる方は、まずは書籍で取り組むのもありです。
自力で認知行動療法に取り組めるように編集された書籍が多数販売されています。ネットの不完全な情報に頼るより、書店でそれらの書籍に目を通してみて、しっくり来たもので練習してはいかがでしょう。
『触れる』の事例
私が「感情ケアプログラム」をおすすめするのは『触れる』があるからです。しかし『触れる』はわかりにくいと思います。今では『触れる』が最も大切だと考えているくらいですが、最初は私もわかりませんでした。伝わることを願って、ある事例を紹介します。
Aさんの通勤ルートにコンビニがあります。交通量の多い幹線道路に面しています。広い駐車スペースが設けられており、車での利用者が多いコンビニです。
車がコンビニから道路に出るには歩道を横切ります。多くの車は幹線道路に出る際、歩行者が通るスペースを開けて入るタイミングを伺っています。しかし、車が歩道を完全にふさいでいることも頻繁にあります。Aさんは、そのようなドライバーに怒りを覚えます。
その日の朝は、Aさんが歩いている目の前を車が横切りました。そして完全に道路をふさぎました。Aさんは強い怒りを覚えました。怒鳴ってやろうかと思いましたが、女性ドライバーだったこともあり、こらえました。
帰宅時にコンビニの前を通ったとき、朝の怒りがよみがえってきました。帰宅してからもモヤモヤが晴れないので、怒りのケアを行うことにしました。
そのときのAさんの状態は、警戒<2倍反応モード>です。朝は怒鳴りたい気持ちを抑えて、その場を離れました。そこで危機対処<3倍反応モード>から脱しています。
Aさんは朝の怒りに『触れる』ことにしました。
朝の出来事を思い出して、怒りをそのまま感じるように心がけました。「怒るのも仕方ないよな」と怒りを否定せずに認めました。怒りの強度が上がったときは、腹式呼吸をして冷まします。
時折、「出口の右側に寄せて止まってたな。運転が下手くそなんやろな。周囲を見る余裕もなかったんやろな」と思考が働こうとしますが、「それは予防段階でやること」「今は思考を脇に置こう」「ただ感じよう」と心がけました。
そうしているうちに、過去の出来事が思い出されてきました。小学生の頃、上級生に泣かされたこと。公園で弟が遊具の順番待ちをしているとき、上級生に割り込みされたのに抗議できなかったこと。などなど、悔しい体験がよみがえってきました。
それらも受身で感じるままにしていました。すると、「ふがいない自分」という言葉が不意に浮かんできました。Aさんは、ハッとしました。
この作業は過去に数回やりました。その経験で思ったのは、過去のドライバーに対する怒りを、目の前のドライバーにぶつけている、いわば八つ当たりのような状態だと考えていました。
「ふがいない自分」という言葉が出てきたとき、「過去の自分のふがいなさを、目の前のドライバーを使って取り戻そうとしているのかも」と思いました。それに気づいたとき、何となく腑に落ちた感覚がして、怒りがスーッと消えていく感じがしました。
解説します。この事例は警戒段階のケアを紹介したものです。まず、怒りの感情を否定せずに、怒りが生じたこと自体を認めました。「怒ってはいけない」と抑え込むのは自己否定です。警戒段階が続きます。その経験は恨み記憶として保存されるかもしれません。
次に、出来事を思い出して、受身の姿勢で怒りを感じました。ただ感じることが大切です。思考が生じたら中断しています。怒りの強度が上昇して巻き込まれそうなときは、腹式呼吸で対処します。
そうしているうちに、過去の出来事が思い出されてきました。そして、「ふがいない自分」という言葉が内側から出てきました。このようなことが毎回起きるわけではありません。起きなくても問題ありません。感情に触れる回数を重ねることで、予防段階へのプロセスが進みます。
以下は夫婦のコミュニケーションをテーマにしたシリーズ記事です。合わせてご覧下さい。