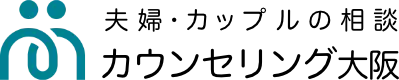「自己責任」の言葉を頻繁に目にするようになりました。「自己責任」の流行によって、「(困ったときでも)他者に頼るのはいけないこと」という空気ができてしまったのであれば、それは誤りです。
困ったときに他者に頼れるのは身につけたい能力
わが家には3人の子がいます。子育ての終わりが近づいていますが、子育てには多くの後悔があります。特に強い後悔は、子どもたちが幼い頃、怒りなどの力でコントロールしていたことです。長男には特に強く当たってました。申し訳ない思いで一杯です。この思いは生涯持ち続けるはずです。
もし、子育てをもう一度やる機会を得られたら、いざというときに、子どもたちが躊躇なく頼れる存在でありたいと思います。子どもたちに、援助希求的態度が育つような関わりをしたいと思います。
【援助希求的態度】問題や悩みを抱えて自分では解決しきれないと感じたときに、誰かに相談したり、 助けを求めたりしようとする態度のこと。
援助希求的態度という言葉が最初に使われたのは平成26年7月1日、文部科学省が作成・通知した、「子供に伝えたい自殺予防(学校における自殺予防教育導入の手引)」及び「子供の自殺等の実態分析」においてのようです。
学校における自殺予防教育の目標として、「早期の問題認識(心の健康)」と「援助希求的態度の育成」の2つがあげられています。
問題や悩みを抱えて自力で解決できないとき、他者に相談したり援助を求めたりするのは、生きていく上で必要な能力です。自殺予防に限ったことではありません。うつ病などメンタルヘルス不調に陥らないためにも必要です。
頼る能力が自主性・積極性が育つ土台となる
エリクソンの社会心理発達理論では、0才から2才くらいまでの乳児期の発達課題は「信頼VS.不信」です。
赤ちゃんは自力では何もできません。泣くことによって空腹などを養育者に伝えます。その訴えが届いて世話を受けることにより、周囲への信頼が育まれます。逆に、この課題をクリアできない場合は、誰も自分を助けてくれないという不信感を持つことになります。
エリクソンの理論の全体像は以下のページをご覧下さい。
「自立とは依存先を増やすこと」という言葉があります。「他者に頼らないことが自立ではなく、助けが必要なときには、それを他者に伝えられることが自立である」という意味です。
以下は自立について書いたブログです。
依存症は、人に依存できない病
「依存症は、人に依存できない病」という言葉があります。
依存症には、薬物などの物質への依存と、ギャンブルやゲームなどの行為への依存があります。依存症の人は、快楽のためにそれらに依存しているという誤解があります。実際は、悩み、苦しみ、焦り、不安などの心の痛みを抱えていて、その痛みを和らげるために、それらに依存しています。
誰かに頼ることができれば、それらに依存する必要はなかったかもしれません。
下記は参考書籍です。14才の読者を想定して書かれた本ですが、大人にも大変役立つ内容です。個人的には、ぜひ子を持つ親に読んでほしいです。
頼る力が自己肯定感を育てる
自分に自信がない人(自己肯定感が低い人)の特徴の一つに「他者に頼るのが苦手」があります。拒絶されることに恐れを感じるからなどが理由です。
自己肯定感と(他者に)頼る能力は、ニワトリが先かタマゴが先かの話です。以下は、自信がなくて他者に頼れない人に起きている循環です。
- (受け入れられる)自信がない
- ➡ 頼れない
- ➡(受け入れられる)経験ができない
- ➡(受け入れられる)自信が育たない
- ➡ ますます頼れない
- ➡ ますます(受け入れられる)経験ができない
- ➡ 繰り返し
この循環を繰り返しているうちは、自己肯定感が育つのはむずかしいでしょう。一方、他者に頼れる人に起きている循環は以下です。
- (受け入れられる)自信がある
- ➡ 頼れる
- ➡(受け入れられる)経験をする
- ➡(受け入れられる)自信が育つ
- ➡ ますます頼れる
- ➡ ますます(受け入れられる)経験ができる
- ➡ 繰り返し
好循環です。頼って断られることもあるでしょう。自己肯定感が低い人は、自分という人格を拒否された感覚になることが多いです。自己肯定感が高い人は、依頼の拒否と人格の評価を分けて捉えることができます。
他者に頼っていいという感覚は、生きていく上で精神的なセーフティーネットになります。
まとめ
- 援助希求的態度とは、問題や悩みを抱えて自分では解決しきれないと感じたときに、誰かに相談したり、 助けを求めたりしようとする態度のこと。
- 他者に頼る能力が、自主性、積極性、自己肯定感を育てる。
- 依存症は、人に依存できない病。
- 子どもの援助希求的態度を育てるのは、親の大切な役割の一つ。





![世界一やさしい依存症入門 やめられないのは誰かのせい? (14歳の世渡り術) [ 松本 俊彦 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7343/9784309617343_1_6.jpg?_ex=128x128)