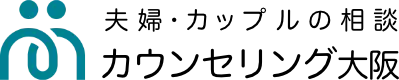子どもの健全な自信を育むことは、親の願いの一つでしょう。自信って何ですか?と聞かれると、答えるのは案外むずかしいと思います。範囲が広いからです。
心理学では自信のことを「自尊感情」といいます。自尊感情に関わる概念は多数あります。最近の流行は「自己肯定感」ですね。自分自身を価値ある存在として感じていることを意味します。自尊感情と同義で使われることもあるようです。
心理学を学んでいる人にとって、テストに出るのでしっかり覚えておきましょうという概念に「自己効力感」があります。「ある課題を達成するのに必要な能力が今の自分にある確信」のことを言います。平たく言うと、「できる」という感覚のことです。
自己効力感とは
「自己効力感」は心理学者のバンデュ−ラが提唱した概念です。テストに出るくらい重要な自分物の1人です。「モデリング(観察学習)」を提唱したことでも知られています。
自己効力感を辞書で引くと以下のように記されています。
自分が行為の主体であると確信していること、自分の行為について自分がきちんと統制しているという信念、自分が外部からの要請にきちんと対応しているという確信が自己効力感である。
出典:心理学辞典 有斐閣
先ほども書きましたが、平たく言うと「できる」という感覚です。「できる」感覚が育つと「自己肯定感」が育ちやすくなります。「自己肯定感」が高い人は失敗に凹みにくいので、「できる」体験をしやすくなります。常にそう単純なものではありませんし、高すぎるのも弊害がありますが、低すぎるのは避けたいです。
自己効力感を育てる4つの要素
恥ずかしながら私はダメな父親です。子どもたちは吹奏楽で全国大会へ行くまでになってくれましたが、それは指導者や仲間のおかげで私の貢献はゼロです。勉強嫌いにさせたのは、怒ることを指導とはき違えていた私の責任です。
私の深い後悔は脇に置いて、自己効力感に影響を与える4つの要素を紹介します。
個人的達成
個人的な成功体験のことです。何らかの課題に取り組んで成功を体験すると、その課題に対する自己効力感が向上します。また、関連する領域への自己効力感も向上します。逆に失敗体験は自己効力感を失わせて、関連する領域への自己効力感も低下させます。
個人的達成を重ねるコツはスモールステップです。達成を一足飛びに目指すのではなく、少しがんばれば届く程度のサイズに分解して(カウンセリングでは絶対に達成できるサイズへの分解を目指します)、成功を経験しやすくします。
私の体験で言うと、2018年の7月から自転車通勤を始めました。もともと身体を動かすのが好きだったので、そんなに苦ではありませんでした。通勤交通費の節約というセコイ考えもありました。
体力に自信がついてジョギングも取り入れるようになりました。50代になっても体力の向上が可能であることを経験してモチベーションが上がりました。高血圧と高尿酸の健康問題を抱えていたので、そのモチベーションのままダイエットすることにしました。
最も太っていた時期は80kgでした。今は67kg前後で安定しています。動画を撮ったのは80kgの頃だったと思います。
お子さんには、スモールステップでの達成経験をたくさんさせてほしいと思います。
代理学習(モデリング)
他者の達成を観察することにより自己効力感を育てることです。観察学習と言われることもあります。観察の対象となる人のことをロールモデルといいます。代理学習の効果を得やすいのは、ロールモデルが自分と似た環境や経験を共有していることです。野球少年にとってイチローは、ロールモデルとしてふさわしくないかもしれません。
今や全国大会で優勝するには、全国からトップレベルの選手をスカウティングするのが当たり前のようになっています。全国に手は届かないけれど、地区では常に好成績を残す公立校があります。先輩たちと一緒に練習することが代理学習になっているのだと思います。
言語的説得
言葉による説得や励ましのことです。何かを達成したとき、「よくやった」と適切なタイミングで適切なフィードバックを受けると、自己効力感が向上します。新たな課題に取り組むとき、「あのようにやれば大丈夫」という励ましも効果的でしょう。
肯定的でわかりやすい言語的説得を受けることで自己効力感が向上します。特に本人にとって大切な人、重要な人、信頼している人からの言語的説得は自己効力感を向上させます。恩師や憧れの人からの一言が、今も自分を支えてくれているという人もいると思います。
情緒的覚醒
心や身体の反応も自己効力感に影響します。緊張が大きいと自己効力感は低下します。緊張が大きいと身体に力に入り、パフォーマンスを発揮しにくくなります。それを自覚すると自己効力感が低下します。適度にリラックスしているときは、身体の力が抜けて、ゆったり呼吸しています。パフォーマンスを発揮しやすい状態です。自己効力感は高くなりやすいです。
思考、心、身体は互いに影響を与え合っています。物事をネガティブに考える傾向の人は、気持ちもネガティブに振れがちです。自己効力感が低くなりやすいです。物事を楽観的に考える傾向の人は、気持ちも楽観的に振れやすいです。自己効力感が高くなりやすいです。
自己効力感は高ければ良いということでもない
コーチングやNLP(心理学のエッセンスを取り入れた自己啓発)を学んでいる人は、「根拠のない自信を持つ」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。自信はないよりあるほうがいいと思いますが、根拠のない自信を持ちすぎるのは危ういです。
根拠のない自信が高すぎるがために、状況判断が甘くなり、準備をおろそかにして、望む結果を得られない、といったことがあります。軽装で冬の山に登る人の中にも、そのような人がいるのかもしれません。根拠のない妄想ですが。
不安や恐れは、「備えなさい」「回避しなさい」のサインでもあります。大きすぎるのも、小さすぎるのもよろしくありません。自信も同じでしょう。良いバランスを如何にして見つけるかです。
こうして書いてみると、育児は育親であると改めて感じます。