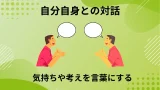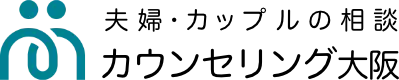パートナーに大学同窓会の参加を嫌がられる。「なぜ?」と聞くと、「嫌だから」。「なぜ、嫌なの?」と聞くと、「どうして参加する必要があるのか理解できない」。嫌な気持ちも理解できるけど、嫌と言われるだけでは受け入れられない。
感情的な会話になりがち
冒頭の例はサークルの同窓会でしたが、会社の懇親会、友人たちの飲み会などの機会があります。サークルの同窓会だと、そこに元彼、元カノがいることもあり、更に状況をむずかしくします。
このような会話に見られるのは、同じ言葉を繰り返すことにより、お互いにイライラしてきて、喧嘩になってしまうことです。「何度言わせるの!」「嫌を繰り返されてもわからない!」というパターンです。
このような状況で行われている会話は、例えば以下のようなものです。
「内容より感情をぶつけられる会話が苦痛です」と訴えられるケースはめずらしくありません。
感情的になる理由
パートナーの不快感は、多くの人が何となく理解できると思います。しかし、「嫌」の一言で済まされること、ちゃんと説明されないこと、感情をぶつけられることで、一方的すぎると不快になります。
感情的になる理由として考えられるのは以下の悪循環です。
お互い疲れてしまいそうです。
「嫌」を別の言葉で表現すると
「嫌」で訴える気持ちを推測すると、以下のようなものがあげられます。
二人の関係性や歴史にもよりますが、多少の嫉妬や不安が生じるのはもっともなことだと思います。ただし、程度の問題でもあります。
なぜ「嫌」としか言えないのか
「嫌」という表現になるのは、理由を適切に表現できないことがあるようです。もっとも、自分の気持ちを適切に表現するのは、案外むずかしいものです。だからこそ、認知行動療法には、認知再構成法と呼ぶ自分の気持ちを言語化する技法があります。この技法は後ほど紹介します。
「嫌」という表現になってしまうのは以下の要因が考えられます。
次に改善策を検討します。
感情を理解する方法
感情を理解する方法として、感情日記と認知再構成法を紹介します。
感情日記
自分の感情の理解度を上げるには、感情日記はオススメです。その日に経験した感情を思い出し、言葉で表現します。ノートやスマホのメモなどを利用します。一行でも構いません。「うれしかった」「イラッとした」など一言でも構いません。
続けているうちに、「上司はいつも気にかけてくれている。その気遣いがうれしい」「あの営業は仕事が雑で毎回尻拭いさせられる。軽く見られているようでイラッとする」のような文になっていきます。感情の解像度が上がっていきます。
認知再構成法
認知再構成法は、認知行動療法の技法の一つです。自分をつらくさせる偏った思考に気づき、現実的な思考を選択する技法です。自分の感情だけではなく、パートナーの感情の理解にも役立ちます。
実例を見るのが早いと思います。
| 出来事 | 思考・解釈・意味 | 感情 |
|---|---|---|
| 帰宅した夫は私の挨拶に応えなかった | 私の存在を無視している 私を大切に思っていない 私に怒っている | 悲しい さびしい こわい |
| 食事中、夫は私の問いかけに返答しなかった | 私の話を聞く気がない 私に興味がない 私に怒っている 私を大切に思っていない | さびしい 悲しい こわい 不安 |
| 夫は玄関のドアを乱暴に閉めた | 私に怒っている 私の存在を無視している | こわい 悲しい |
相互理解に至らない会話では、「出来事」と「感情」しか言葉にされていません。「あなたは私の挨拶をスルーした」と「出来事」だけを話す例もあります。「スルーした」「悲しい」より、「スルーした」「私をどうでもいいと思っている」「悲しい」のほうが、より伝わると思いませんか。
伝える前に言語化です。その「出来事」があったとき、どのような考えが頭に浮かんだのか(思考)、どのように受け取ったのか(解釈)、それは自分にどのような意味があるのか(意味)を言葉にします。最初はむずかしいと思います。それでも、がんばります。
この枠組みが定着すると、他者の考えや気持ちを推測しやすくなります。相手の感情の理解力も高まります。
こうして明確になった自分の感情を「私は(自分の感情)と感じる」という形で伝えます。私が主語なのでアイメッセージと呼びます。アイメッセージを始めとするコミュニケーションについては、以下のシリーズで詳しく説明しています。